Jan, 2008

高速を走る車内でウイノーナがさかんに「家がおんぼろで恥ずかしい。」と言っていたが,二人の住まいは素敵なアメリカンスタイルの平屋だった。タルサ中心街の東を南北に貫くペオリア通り南から小道を西に入った三軒目にある。

通りに面した芝生は隣家とつながっていて,白いペンキの壁に青い窓枠がおしゃれだ。

窓にはウイノーナの愛猫のミミがひなたぼっこしている。

大きな郵便物は木製の洗濯バサミに挟んでいってくれる。

中に入ると広いリビングにはグランドピアノが置いてありベッドルームが二つ,明るくて広いキッチン。棟つながりに屋根のあるガレージ。


ダイニングの扉からテラスに出るとテニスコートほどもある庭にはリスが走っている。

「ほええ,かっこいい。ど,どの辺がおんぼろなんだよ。」
ウイノーナは全く変わっていなかったが,ぱっと見,外見から日本人っぽさが薄れてもうハーフには見えない。

「あなたたちこそちっとも変わってない。」
とウイノーナが嬉しそうに言う。そう,ボクたちもウイノーナと同じく4年前と変わらない。

ネイサンはどうだろう。
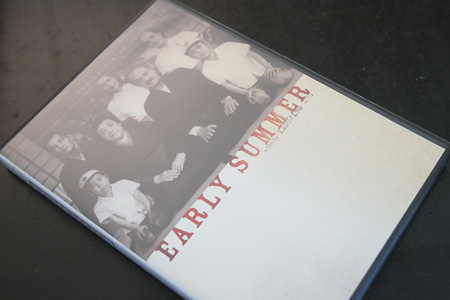
ネイサンは小津安二郎に凝っていた。
原節子のファンだという。
4年前に東京でボクと約束したとおり,彼は日本語の勉強を続けていた。邦画のDVDはその教材として買ったのだろう。ボクは自分の英語力の低下を強く恥じた。
「オオ!シュイチ,ドレーミ,ようこそタルサへ,よく来てくれました。」
職場からネイサンがお昼を食べに帰ってきた。顔を合わせた四人はお互いが変わっていないことを確かめた。正確に言うと,ウイノーナの容姿は日本人離れし,ボクのメガネは遠近両用になって,ドレミの英語は少し衰え,二枚目ネイサンのお腹はわずかにたるんでいたが誤差の範囲である。
お昼ごはんはウイノーナの十八番のシチュー,ほろほろに煮たスジ肉とジャガイモの相性がとってもよい。本来なら昨日の夜,歓迎の宴で囲むごちそうだったはずだ。
忙しい思いをさせた。料理ばかりでなく,きっとウイノーナは昨日,朝から料理と大掃除に追われていたことだろう。部屋の隅々まで清潔に掃除が行き届いている。
彼らにお土産を渡すために開いたトランクの中を見てネイサンが声をあげた。
「Oh!! Amazing.(びっくりー!)」
あまりに整頓されたドレミの荷作りに驚いたのだ。ある程度整理整頓が得意な人が見てもドレミのトランクは十分驚嘆に値する。まして彼ら夫婦は整理整頓があまり得意ではない。こんなに家中をキレイに片付けてしまって,ボクらの帰国後,あれやこれやと行方不明になるものが続出することだろうと危惧される。
変わらないと言えば二人の車。ソルトレークシティに二人を訪ねた9年前と同じマツダのファミリアセダンが赤白二台だ。そっと赤い方のオドメータを覗くと17万キロを超えていた。ソルトレークの大学に行くとき父親のトムがウイノーナに買ってあげたのが白いマニュアル車で赤いATは弟のケブンの車だ。ニューヨークからソルトレーク,ヒューストンそしてタルサと二人についてきたのだ。この型のファミリア(もっとも北米やヨーロッパではマツダ323という名だと思うが)が現役なのはかなり希少といえる。
「和食パーティーはいつにしよう。」
「明後日はどう?」
「よっしゃ!アメリカ人の友だちも呼んだら?」
「いいの?」
「そりゃあ,それがお土産なんだから。どーんとまかしときー。」
実は行く前にお土産は何がいいかウイノーナにメールで尋ねたところ「日ごろ仲良くしている日本人ダンサーを招いてshuの和食をご馳走したい。」と返信があったのだ。トランクには醤油やみりんなどの調味料を準備してきてある。
「じゃあ食いしん坊のアンソニーに電話してみるよ。」
ネイサンが携帯電話をかける。もの静かだが茶目っ気のあるいつもの話し方でネイサンが招待の主旨を語る。
「ぐっっっれぇいと!!」
われがねのような声が電話を通してすらガラスを震わせた。
「★○◇$#&○☆★!!!」
たぶん期待と感謝を伝えていると思われるが,まるで逆転ホームランに興奮したアナウンサーの声だ。ネイサンは受話器から遠く耳を離しながらウインクした。
「ま,まかしてくれ…」
ボクは胸をたたいてみせた。けれど果たして逆転ホームランほどの期待に応えられるだろうか。

「shuとドレミはスクーター乗らないの?」
そう言いながらネイサンは自慢の新しいスクーターに乗って出勤していった。
午後はドレミのショッピングに付き合って終わった。ドレミはショッピングが大好きだが買うものは高が知れている。ボクのTシャツとか自分の下着など日本では手に入らないものを買っている。高価なものではない。


近所の高級住宅街などを散策して帰宅した。

友だちの家に上がらせてもらったが,いやはやバスルームだけで7,8個はある。

帰宅するとネイサンが先に帰っていて,
「パーティーに誘った人たちみんな来るってよ。」
とにこにこしながらウイノーナに言う。
「多いんじゃない?数えてみてよ。」
「うん」
ウイノーナに促され,ネイサンが指を折り始める。細くしなやかなピアニストの指だ。
「まずアンソニーと奥さん,赤ちゃんがふたり…」
「赤ちゃんはいいの」
「ロバートと奥さん,赤ちゃんひとり」
「だから赤ちゃんはいいの!」
「オーケー,JJに奥さん,赤ちゃんはまだ…」
指が二巡目も半ばを過ぎた。
「16人かな」
「16人!!多すぎるわよ。」
「大丈夫,アンソニーの家を借りることにしたよ。大歓迎だってさ」
「そうじゃなくてshuとドレミがムリよ!」
「あ,そうか。」
みるみるネイサンがしょんぼりするものだからボクは努めて明るく言う。
「たははは,なーんだ,16人くらい軽い軽い。」
もちろん強がりだ。
「ホントに大丈夫?」
今さらムリだとは言えない。おそらくロバートだのJJだのも電話で
「グレイト!オレ,日本食,食べたことないんだよ。楽しみだなあ。」
「shuのは美味しいんだよ,ボクも大好きさ」
…くらいのやり取りはあったはずだ。ウイノーナが尚も不安そうにしているのを見てドレミが言った。
「ちょうどいい人数よ,ウイノーナも手伝ってね。」
こうしてボクはコンロ(ストーブと呼びます)の付け方すらわからないキッチン,味の想像もつかない食材,日本から持参したわずかな調味料…という凄まじい条件のもとで,16人のゲストを迎える和食パーティーのシェフとなった。
タルサの最初の夜は近所で評判のベトナム料理の店に行った。ご馳走したいと二人は言うが,彼らの質素な生活を見ればあまりお金を使わせられない。音楽で生活していくのは大変なことだろう。だけど二人は信念を変えない。その代わり目はいつも生き生きしていて楽しそうだ。母が彼らへのお土産代わりに100ドルをボクたちに託していた。
「今夜の晩餐はshuのお母さんのおごりよ。だからぱーっと頂きましょ。」
ドレミがいいことを言った。料理が運ばれてきた。
ひとつ大きな問題がある。彼らは敬虔なモルモン教徒なのだ。モルモンの信者は彼らのように純真で心優しい人が多い。反面その戒律は厳しく,酒,タバコはもちろん,カフェインの入ったお茶も飲むことを禁じられている。今回はまず最初に彼らの前で飲酒することがどれくらいマナーに反するかを聞いてみた。二人は全く問題ないと快く答えた。実際,勤め先のパーティーや楽団の打ち上げなどで,酒席に参加せざるを得ないときもあると言う。ボクたちは迷ったが誘惑に屈して,バドワイザーを注文した。

しかしどうもいつものように,プハーっというわけにはいかない。ついお上品にお抹茶をいただくような手つきになってしまったりする。
それなのに時差ぼけも手伝って酔いだけは強烈に回ってきた。家に帰る道々,ともすれば千鳥足になるボクをドレミが目でたしなめる。全くわが女房どのは酒に強い,酔ったそぶりも見せずにウイノーナたちと他愛のないお喋りをしながら歩いてゆく。ボクなどは酔うほどに英語を見るのも聞くのも嫌になり車の騒音にまぎれながら,
「土佐のぉ~高知のぉ~はりまやぁばぁしで~♪」
などと唸る。去年の春は土佐四万十川に旅していた。菜の花が咲き乱れる清流で愛犬タローは初めて泳いだのだ。タローはどうしてるかな。そんな感傷から思わず口ずさんだ「よさこい節」を,この夜意外な形で聞くことになる。
家に帰ったボクは日本に宛てた絵はがきを書いた。午後のショッピングの間,あれこれ見て回ったが予想通りお土産になりそうなものはない。東京に住む人にはなんちゃって巨大食品を買い,遠くの人には絵はがきを送ることにした。
居間からはネイサンのピアノが聞こえる。まだ着いたばかりで,葉書に書くことがないので,欠航騒ぎのネタを酔筆でしたためているとネイサンとドレミに呼ばれた。
「これはどんな曲ですか?」
アップテンポで演奏される曲に耳を傾ける。
「ん?おどまぼんきりぼーんきり…五木の子守唄じゃん,」
ピアノに合わせてボクが歌ってみせると,せつない歌詞の意味が伝わるのかピアノの曲調が変わった。
「そう,こりゃララバイだよ。ラルゴ,ラルゴ」
「なるほど,じゃ,これは?」
「わからない。」
楽譜を見ると「木更津甚句」とある,こんな調子で次々に日本の歌を弾いては曲の意味を尋ねた。,民謡,童謡,「上を向いて歩こう」から果てはさっき路上で歌っていた「よさこい節」まで出てきた。

ボクたちはネイサンの指揮するオーケストラを聴いたことがない。オケの関係者がもしこれを読んで下さっていたらいかがでしょう。「五木の子守唄」を瞬時に理解できる指揮者をやとってみませんか。
日本の曲に限らすネイサンのレパートリーは多い。彼の仕事はクラシックバレエの練習中の生演奏だ。ウォーミングアップ中には次第に上がってゆく調子で,レッスン中はコーチや演出家の指示に合わせて即興で音楽をつけていく。ボクの素人考えだが,練習中の曲にダンサーの意識や動きが音楽とシンクロしないように,また,彼らの気分がリフレッシュするよう,メロディーを常に変えていく必要があるのではないだろうか。今,ネイサンが所属するバレエ団には日本人のダンサーも数人いるので日本の曲もたくさん演奏しているらしい。けれどもそれらの曲は(ボクの母ならすべて歌えるであろうが)ボクたちですら半分くらいしかわからない。まして若いダンサーたちは,たぶん日本の歌だと気づいていないだろう。
それでも遠くオクラホマのレッスン場で青い目のダンサーたちが「木更津甚句」に合わせてクラシックバレエを踊っているというのはなかなか楽しい光景ではないか。
ネイサンが今度はマックにDVDをセットした。ジャケットには「EARLY SUMMER」とある。

「ドレミにお願いがあります。」
と言って出してきたノートには映画の場面の会話が書き込んであり,ところどころに空白のアンダーラインがある。

いっしょに映画を見て空白を埋めて欲しいというのがお願いだった。

「EARLY SUMMER(初夏)」原題は「麦秋」
監督:小津安二郎
出演:菅井一郎 原節子 笠智衆 杉村春子
国内では忘れられていた小津作品はフランスの研究者の間で再評価され外国でブレイクした。
冒頭,朝食のシーンが液晶モニタに映る。卓袱台で紀子(原節子)が朝食を食べながら甥っ子に洗顔を促すと,甥っ子はこっそりタオルだけを濡らしてくる。「ホントかしら」と紀子は偽装に気づきながらも彼にごはんをよそう。
「次です。」
とネイサン。紀子の義姉が子どもに声をかけたところでポーズをかける。
「さっさとおあがんなさい…」
耳を澄ませていたドレミが発音すると,ネイサンが鉛筆でノートの空欄に書き込む。
「…オアガンナサイ…どういう意味ですか?」
北鎌倉に住む上流家庭が舞台らしく,婦人たちの使う言葉は美しい(とボクには感じられる)。少なくともボクが子どもの頃までは,上流家庭でなくとも女性たちの言葉はこんな風だった。現代の若いお母さんの半数は,こんなとき「ほら,とっとと食えよ。」と言う。その違いを追求されて「若い人たちの使う言葉は現代語だ」とはなぜか言いたくなくて,つい「育ちの違い」と説明してしまった。
「グズねえ」
と画面の原節子が言う。
「グズ…ドレミは使うか?」
「使わない。」
「じゃあ紀子は育ちが悪いのか。」
「子どもに対してや親しい間柄のプライベートな会話ではバカと同じく使う。」
「バカも使う?」
「そう,例えばshuに,…バカね。」
「なるほど」
これは英語でも同じようなものだろう。今度は父親役の菅井一郎が郵便物を持って居間に登場する。
「これ出しといてくれ」
出し-て-おい-て-くれ…こちらは文法的に説明が難しい。
場面変わって紀子が秘書として働く丸の内あたりのオフィスの一室。キザな重役(ネイサンのノートにはボスと書いてある)が紀子と話しているところに料亭の若女将(淡島千景)が着物姿でツケの集金にくる。共通の知り合いが心臓病を悪化させたと聞いたときのキザボスの台詞。
「だいじょうぶ。あのババア,くたばりゃしないさ。」
言わない,言わない。
「映画やテレビでしか聞かない日本語だよ。」
たぶんキザボス氏は育ちが悪いのだろう。

こんな調子でドレミは滞在中,毎夜ネイサンに付き合い最後の日にはとうとうネイサンの用意したノートの空欄がすべて埋まったのだった。
「んー,デタラメ デスネー。」
書き起こしが全部終わり,ドレミにお礼を言ったあとでネイサンは日本語でこう感想を述べた。もちろん映画やドレミがでたらめという意味ではない。自分の書き取っていた台詞がずいぶん違っていて恥ずかしいと言いたいのである。
「そんなことない,よく書けてたわ。」
ドレミが言った。ボクもまったく同感である。